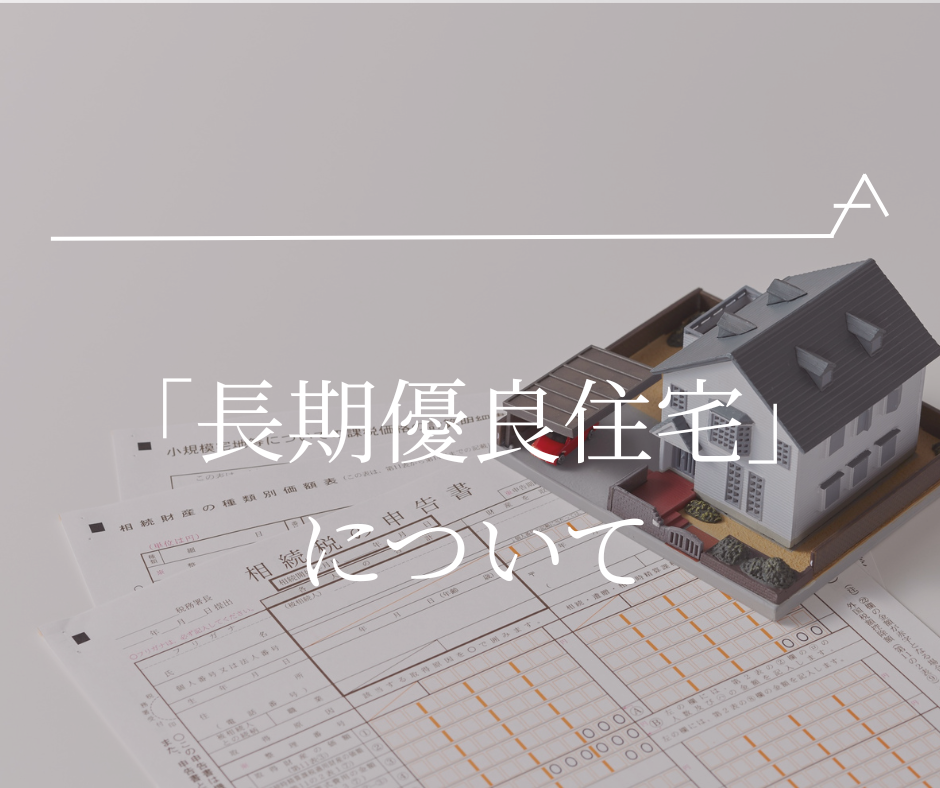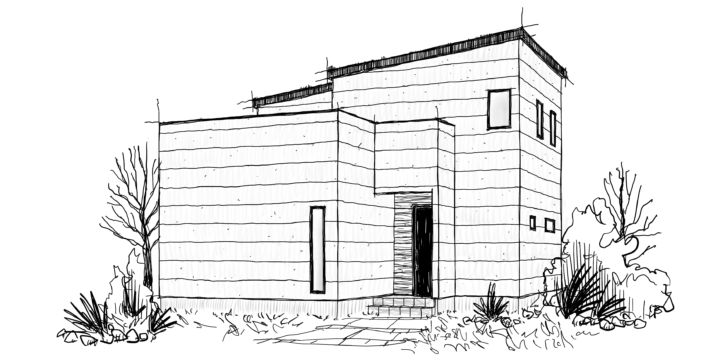- スタッフブログ
- 担当:よこたますみ
耐震等級について
- 公開日:2025/10/04
- 更新日:2025/10/04

こんにちは、営業部の横田です。
今回のテーマは「耐震等級」について。少しでもご参考にしていただければ嬉しいです。
日本は世界でも有数の地震大国です。そのため住宅の安全性を測る基準として「耐震等級」が導入されています。
これは住宅を建てる際に「どの程度の地震に耐えられるか」を明確に数値化したもので、住宅購入者や建築主が安心して家を選べるようにするための指標です。
特に注文住宅を検討している方にとっては、単なる知識にとどまらず、建築費や将来の資産価値に直結する重要なテーマといえます。
〇 耐震等級の基本的な意味とは?
耐震等級とは、住宅性能表示制度の一部として国が定めた「住宅の耐震性能を示す指標」です。
等級は1~3まであり、それぞれの基準は大地震に対する耐久性を数値的に表しています。
耐震等級1:建築基準法に定められた最低限の耐震性能。数十年に一度発生する震度6強〜7程度の地震でも倒壊・崩壊しないことを想定。
耐震等級2:等級1の1.25倍の耐震性。主に学校や病院など災害時の避難施設として利用される建物に求められるレベル。
耐震等級3:等級1の1.5倍の耐震性。消防署や警察署といった防災拠点に相当する最も高い水準。
つまり耐震等級は、「家がどのレベルの地震にどれだけ耐えられるか」を明確にしたものです。
〇制度を定める国の基準と仕組み
耐震等級は、国土交通省が定める「住宅性能表示制度」の一環として設けられています。
この制度は2000年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、住宅の性能を客観的に評価するために作られました。
評価は第三者機関によって行われ、設計段階での「設計住宅性能評価」と、建築完了後に行う「建設住宅性能評価」の2種類があります。
これにより、建築主や購入者は「自分の家がどの耐震等級に該当するのか」を書面で確認でき、安心して住宅選びができる仕組みとなっています。

〇耐震等級1・2・3の違い
耐震等級は単なる数字の違いではなく、住宅の安全性や将来的な安心度を左右する重要な基準です。
注文住宅を建てる際に「どの等級を選ぶか」は、家族の命を守るだけでなく、建築コストや資産価値にも大きな影響を与えます。
ここでは、それぞれの等級の具体的な違いや特徴を詳しく見ていきましょう。
①各等級のメリットと注意点
耐震等級には、それぞれメリットと注意すべき点があります。
耐震等級1
・建築費を抑えられる。
・ただし「最低限の基準」であり、大地震後に居住継続が難しくなる可能性がある。
耐震等級2
・費用と性能のバランスが良い。
・学校や病院と同レベルの安心感。
・ただし、資産価値の面では等級3に劣る場合もある。
耐震等級3
・最も安心できる耐震性能。地震保険料の割引率が最も高い。
・資産価値や将来の売却時に有利。
・ただし、建築費用がやや高くなる傾向がある。
選択のポイントは「予算」と「安心感」のバランスです。
②一般住宅でよく選ばれる等級
現在、注文住宅において最も選ばれているのは耐震等級3です。
特に大地震を経験した地域では「等級3でなければ安心できない」と考える施主が増えています。
一方で、コストを重視する人は等級2を選ぶケースもあります。
耐震等級1は「法律上建てられる最低限の家」ですが、注文住宅として建てる際にはほとんど選ばれません。
つまり、現代の住宅市場では「耐震等級3が標準」「等級2はコスト調整の選択肢」という位置づけになっているのです。
〇耐震等級と建築コスト・資産価値
耐震等級を上げることは、単なる「安心感」だけではなく、建築費用や地震保険料、さらには将来の資産価値にまで影響を及ぼします。
ここでは、実際にどの程度のコストがかかり、どのような経済的メリットがあるのかを解説します。
①等級を上げた場合の建築費用の目安
耐震等級を高めるためには、構造材を強化したり、耐力壁を増やすなどの工夫が必要となります。
その結果、建築コストは一般的に 数十万円〜100万円程度 上がるケースが多いです。
耐震等級1 → 2:木材の補強や壁量の増加が必要になり、数十万円の追加費用が目安。
耐震等級2 → 3:さらに構造計算や金物補強が必要となり、50万〜100万円前後のコストアップが想定されます。
ただし、この費用差は「命や暮らしの安全」「資産価値」「保険料の割引」を考えると、長期的には十分に回収できる投資といえます。
②地震保険の割引と長期的コストの違い
耐震等級を取得すると、地震保険の割引制度を利用できます。
割引率は次の通りです。
耐震等級1:割引なし
耐震等級2:30%割引
耐震等級3:50%割引
つまり、等級3を選ぶことで保険料が半額になります。
住宅ローンを組んで長期的に居住する場合、この差額は数十万円以上に達することも珍しくありません。
「地震後も住み続けられる安心」と「長期的なコスト削減」を両立できる点で、等級3は経済的にも有利といえるでしょう。
③住宅ローンや資産価値への影響
近年は金融機関や不動産市場においても、耐震等級の高さが評価される傾向があります。
住宅ローン審査:一部の金融機関では、耐震性能の高い住宅に対し金利優遇が適用される場合があります。
資産価値:地震リスクの高い日本では、耐震等級3の住宅は中古市場でも買い手が付きやすく、将来的な売却時に有利です。
リフォーム・改修コスト:耐震性の低い住宅は、後から補強工事が必要になる場合があり、その費用は新築時の差額より高額になることもあります。
つまり、建築時に耐震等級を上げることは、将来の資産価値を守る「保険」としての役割も果たしているのです。

〇耐震等級の取得と確認方法
耐震等級は「表示されていれば安心」というものではなく、正しく評価を受けてこそ信頼できる指標になります。
特に注文住宅を建てる際は、設計段階からどの等級を目指すのかを決め、第三者機関の評価を通して証明を得ることが重要です。
ここでは耐震等級を取得・確認するための方法を具体的に解説します。
①設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の違い
耐震等級の評価には大きく分けて2種類あります。
設計住宅性能評価
設計図面をもとに、建築前に耐震性能を確認する制度です。
この段階で耐震等級が認定されれば「設計通りに建てれば等級○を満たす」という証明になります。
建設住宅性能評価
実際の施工後に第三者機関が現場をチェックし、設計通りに建てられているか確認する制度です。
建設住宅性能評価を取得すると、住宅の性能が「設計上だけでなく実際の建物でも確保されている」ことが保証されます。
注文住宅で本当に安心を得たいのであれば、設計+建設の両方の評価を受けるのがおすすめです。
②注文住宅で耐震等級を指定する手順
注文住宅で耐震等級を取得するには、以下の流れを踏むのが一般的です。
建築会社に耐震等級を希望する旨を伝える
打ち合わせの初期段階で「耐震等級2以上を希望」などと明確に伝えることが大切です。
構造計算や設計図で確認
耐震等級を満たすためには、建物全体の構造計算が必要です。ここで必要な壁量や補強部材が決まります。
第三者機関に評価申請
設計住宅性能評価を申請し、耐震等級を正式に認定してもらいます。
施工後の確認
建設住宅性能評価を受けることで、設計通りに施工されていることを保証できます。
つまり「依頼先に任せきりにせず、評価を取得する流れを理解しておくこと」が安心の第一歩です。
〇注文住宅で耐震等級を選ぶポイント
注文住宅を建てる際、「どの耐震等級を選ぶか」は家族の安全、建築コスト、将来の資産価値を左右する大きな判断です。
単純に「一番高い等級が良い」と考える方も多いですが、ライフプランや予算、住む地域の地震リスクなどによって最適解は変わります。
ここでは、耐震等級を選ぶときに考慮すべき具体的なポイントを解説します。
①家族構成やライフプランに合わせた選び方
耐震等級の選び方は、住む人のライフスタイルや家族構成によっても異なります。
小さなお子様がいる家庭
大地震後も自宅で生活を継続できることが重要になるため、等級3を選ぶメリットが大きいです。
高齢者と同居している家庭
避難生活が長期化すると大きな負担となるため、等級3を推奨します。
単身や夫婦のみで暮らす場合
コストを重視するなら等級2でも選択肢になり得ますが、将来的な資産価値を考慮するとやはり等級3の方が安心です。
長期的に同じ家に住む予定がある場合
長期間安心して暮らすためには、建築時に耐震等級を上げておくのが合理的です。
つまり、「避難生活を避けたいかどうか」が選択の大きな分かれ目になります。
②ハウスメーカー・工務店選びで確認すべき点
耐震等級を確保するには、施工会社の姿勢と技術力が大きく関わります。
標準仕様での耐震等級
会社によっては、標準仕様で耐震等級2や3を取得できる場合があります。見積もりの段階で確認が必要です。
構造計算を行っているか
木造住宅では構造計算が義務付けられていないケースがありますが、等級2以上を取得するなら必須です。
第三者評価の有無
設計住宅性能評価・建設住宅性能評価を取得しているかどうかも信頼性の指標になります。
施工実績と口コミ
過去に耐震等級3で建てた実績がある会社は、ノウハウが蓄積されているため安心です。
施工会社を選ぶ際は「耐震性能をどこまで保証できるのか」を明確にしておくことが大切です。
③耐震等級3は本当に必要?バランスの考え方
「耐震等級3にしたいけれど、費用が気になる」という方も少なくありません。
確かに等級3はコストが上がりますが、その分のメリットは非常に大きいです。
地震保険料が半額になる
将来の資産価値が高い
大地震後も住み続けられる可能性が高い
一方で、地域によっては地震リスクが比較的低いとされるエリアもあります。
その場合、等級2を選んでコストを抑えるという考え方もあります。
結論としては、
「命と暮らしを守ることを最優先にするなら等級3」
「予算との兼ね合いで調整するなら等級2」
という選び方が現実的です。
〇よくある質問
ここでは、耐震等級に関してよく寄せられる疑問に答えていきます。
これらの質問は、注文住宅を検討している方や既存住宅の耐震性を気にしている方から特に多いものです。
Q1: 耐震等級2は弱いと言われるのは本当ですか?
A:耐震等級2は決して「弱い」わけではありません。等級1よりも25%強い構造で、多くの大地震にも耐えられます。
ただし、大規模地震後に「そのまま住み続けられるか」という点では、等級3に劣るケースがあります。
そのため、注文住宅では等級3を選ぶ方が増えているのです。
Q2:耐震等級1の家は震度7に耐えられますか?
A:耐震等級1は「震度6強から7程度の地震でも倒壊・崩壊しないこと」を前提に設計されています。
ただし「損傷を受けても命は守る」という基準であり、居住継続が保証されているわけではありません。
震度7に耐える可能性はありますが、生活を続けるには修繕が必要になることが多いです。
Q3:耐震等級を上げると建築費はいくら高くなりますか?
A:耐震等級を2や3に上げると、構造材の補強や耐力壁の追加が必要となり、建築費は 数十万円〜100万円程度 上がることが一般的です。
ただし、地震保険料の割引や資産価値の向上を考えると、長期的には十分に回収できる投資といえます。
Q4:中古住宅でも耐震等級を確認できますか?
A:新築時に設計住宅性能評価・建設住宅性能評価を受けていれば、耐震等級を証明する書類が残っています。
一方、評価を受けていない中古住宅の場合は「耐震診断」を行うことで、現在の耐震性能を確認可能です。
また、耐震改修工事を行えば、等級相当の性能を確保することもできます。
Q5: 耐震等級3を選べば絶対に安心ですか?
A:耐震等級3は現行制度で最高の水準ですが、「絶対に倒壊しない」という保証ではありません。
ただし、過去の大地震の事例から見ても、等級3の住宅は被害が軽微にとどまるケースが多く、命と暮らしを守る上で最も信頼できる選択肢です。
安心を最大限確保するには、建物の定期点検やメンテナンスも合わせて行うことが重要です。