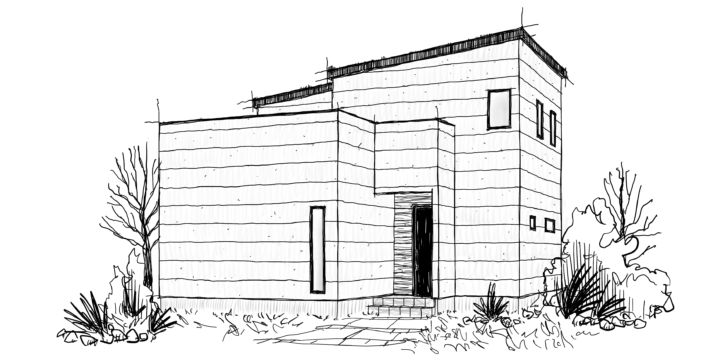- スタッフブログ
- 担当:よこたますみ
「長期優良住宅」について
- 公開日:2025/11/13
- 更新日:2025/11/13
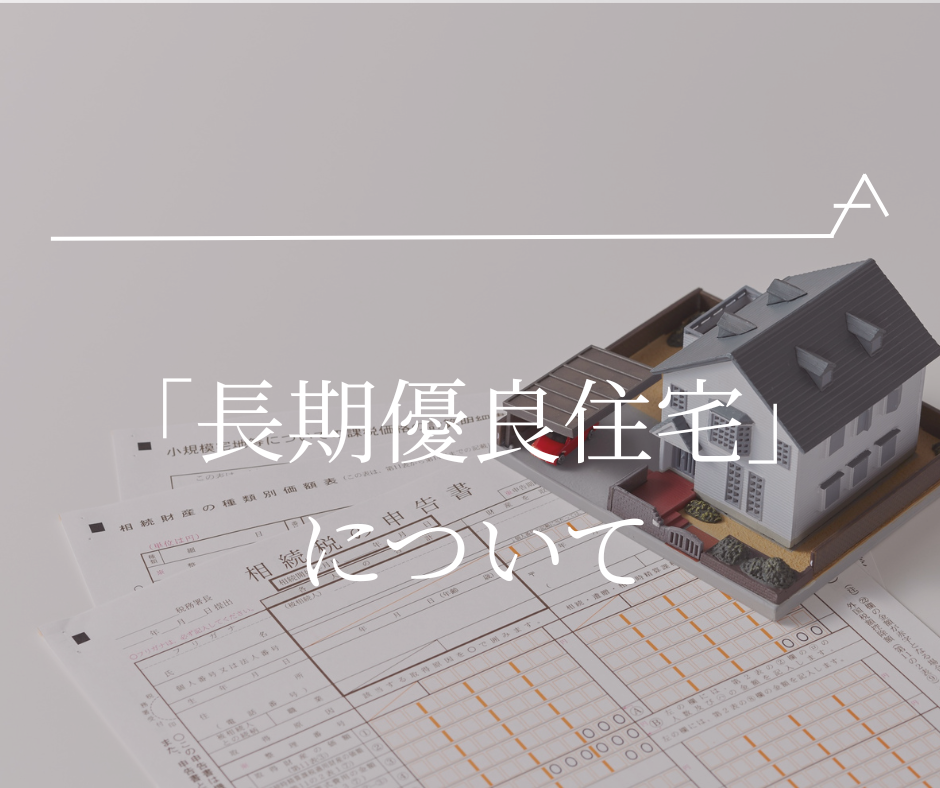
マイホームを検討する際に「長期優良住宅」という言葉を耳にする方も多いでしょう。これは、国が定めた一定の基準を満たす“長く安心して住み続けられる住宅”を指します。住宅の質を高め、メンテナンスを行いながら長期間使用することで、家計にも環境にも優しい住まいを実現することを目的としています。
かつての日本では「住宅は30年で建て替える」という考え方が主流でした。しかし、少子高齢化や環境問題が進む中で、「良い住宅を長く大切に使う」という価値観へと変化しました。こうした社会背景から誕生したのが、長期優良住宅制度です。
制度の定義と誕生の背景
長期優良住宅制度は、2009年に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって生まれました。これは、国が住宅の品質向上と長寿命化を推進するために導入した制度です。
この制度の目的は、単に「長持ちする家」を建てることではありません。
建て替えを繰り返すことで発生する廃材やCO₂排出の削減、そして次世代に価値ある住宅を残す社会づくりを目指しています。
また、長期優良住宅の認定を受けることで、耐震性・省エネルギー性・維持管理性など、一定水準以上の住宅性能が担保されるため、住む人の安心感にもつながります。
国土交通省が定める基準に基づき、住宅の設計段階から行政に申請し、審査を経て「長期優良住宅」として正式に認定されます。
一般住宅との違い・制度が生まれた目的
一般的な住宅と長期優良住宅との最大の違いは、“長く良好な状態で使用するための計画と性能が備わっているか”という点です。
通常の住宅は、建築基準法を満たせば建築可能ですが、長期優良住宅はその上をいく性能と維持計画が求められます。
たとえば、
耐震性: 地震の揺れに対して倒壊・損壊しにくい構造
省エネルギー性: 断熱性能・気密性能の高さ
劣化対策: 構造材の腐食やシロアリ被害を抑える工夫
維持管理のしやすさ: 配管交換などが容易な設計
これらを満たすことで、住宅の寿命を60年以上に延ばすことを目指します。
制度が導入された背景には、「スクラップ&ビルド型」から「ストック型社会」への転換があります。長く住み続けられる良質な住宅を増やすことで、住宅資産の価値を維持し、国全体としても持続可能な社会を築く狙いがあるのです。
〇認定基準を具体的に解説

長期優良住宅として認定を受けるには、国が定める複数の性能基準をすべて満たす必要があります。これらは単なる耐久性の高さだけでなく、「長く快適に住み続けられる」ことを目的とした総合的な基準です。
ここでは、その主な項目とそれぞれの具体的な内容を詳しく解説します。
主な性能項目(劣化対策・耐震性など)
長期優良住宅の認定では、まず「住宅の構造と安全性」に関わる性能が重要視されます。特に注目すべきは以下の項目です。
劣化対策:住宅の構造躯体(柱・梁・土台など)が少なくとも75〜90年程度使用可能な耐久性を確保する必要があります。
具体的には、防腐・防蟻(シロアリ)処理の徹底、床下の通気確保、劣化しやすい箇所の点検・補修を容易にする設計が求められます。
耐震性:地震大国・日本において欠かせない要素です。
長期優良住宅は、「耐震等級2(建築基準法の1.25倍の強度)」以上が必須です。災害時にも倒壊や大破を防ぎ、家族の命と資産を守ります。
省エネルギー性:断熱性能や気密性能を高め、冷暖房エネルギーを削減します。
「断熱等性能等級5」または「一次エネルギー消費量等級6」など、高水準の省エネ性能が必要です。これにより、夏は涼しく冬は暖かい快適な住まいが実現します。
維持管理・更新の容易性:配管や設備を交換しやすいように、点検口を設けるなどの工夫が求められ、将来的なリフォームやメンテナンスを容易にし、住宅を長持ちさせるための仕組みです。
これらの性能を高めることで、長期にわたって住まいの価値を維持できるだけでなく、日々の生活の安心・安全も確保できます。
1.住戸面積・居住環境・維持保全計画の基準
構造や性能面だけでなく、「住みやすさ」や「将来の維持管理計画」も評価の対象になります。これらは住宅の快適性と持続性を左右する重要な要素です。
住戸面積の基準:一戸建ての場合は原則として75㎡以上(少なくとも1階部分の床面積は40㎡以上)と定められています。これは、家族が長期にわたって快適に生活できる広さを確保するための基準です。
居住環境への配慮:良好な景観や地域環境との調和が求められます。たとえば、周辺環境や街並みに配慮した設計、地域コミュニティの形成に寄与する住まいづくりが評価対象となります。
維持保全計画の策定:長期優良住宅の大きな特徴がこの項目です。
所有者は、定期点検・補修のスケジュールを明記した維持保全計画を作成し、行政に提出する必要があります。
この計画に基づいて定期的に点検を行い、住宅の品質を長期的に維持することが求められます。
これらの基準により、単に「性能が高い住宅」ではなく、「世代を超えて価値を保てる住宅」としての条件が整います。
2.新築・改築・既存住宅での違い
長期優良住宅の認定は、新築だけでなくリフォームや既存住宅でも取得可能です。ただし、条件や審査のポイントにはいくつかの違いがあります。
新築住宅の場合:設計段階から長期優良住宅の基準を満たすように計画し、建築前に認定申請を行います。設計者・施工業者と連携して、基準を満たす仕様書を作成することが重要です。
改築(リフォーム)住宅の場合:既存の建物を改修し、性能を向上させることで認定を受けられます。特に耐震補強や断熱改修などがポイントになります。
既存住宅(中古住宅)での認定:購入後に認定を受けるケースでは、専門家による現況検査(インスペクション)が必須です。そのうえで、性能不足の箇所を改修し、必要な基準を満たすことが条件となります。
このように、長期優良住宅は「新築だけの制度」ではなく、既存住宅の資産価値向上にも貢献する制度です。特に中古住宅市場の活性化やリノベーション需要の高まりに合わせて、今後さらに重要性が増していく事が予想されます!
〇取得すると得られるメリット

長期優良住宅の最大の魅力は、「安心・快適に長く住めること」に加え、税制優遇や資産価値の維持といった経済的メリットが多い点にあります。
ここでは、制度を利用することで得られる主なメリットを3つの視点から詳しく見ていきましょう。
1.税制優遇(住宅ローン控除・固定資産税軽減など)
長期優良住宅の認定を受けると、国が定める各種税制の優遇措置を受けられます。代表的なものを以下にまとめます。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)
通常の新築住宅に比べて控除対象となる借入限度額が高く設定されています。
たとえば、一般住宅が「3,000万円」なのに対し、長期優良住宅では「5,000万円」まで拡大される場合があります(制度改正により変動あり)。
控除額が増えることで、10年間で数十万円〜100万円以上の節税効果が期待できます。
固定資産税の軽減措置
新築住宅の場合、3年間(長期優良住宅は5年間)にわたり固定資産税が半減されます。
木造2階建て住宅などでは、年間数万円の税負担軽減が見込まれます。
登録免許税・不動産取得税の軽減
登録免許税(保存登記・移転登記)や不動産取得税でも、長期優良住宅は軽減率が高く設定されています。
特に土地・建物両方を取得するケースでは、トータルで10万円〜20万円程度の節税になることもあります。
これらの優遇は、国が「長く良質な住宅を増やす」ことを目的に制度化しているため、非常に手厚く設計されています。
初期コストが多少高くても、長期的に見れば実質負担を軽減できるのが大きな利点です。
2.将来価値/維持費低減という長期視点のメリット
長期優良住宅は、住宅の品質が国に認められているため、資産価値が下がりにくいという特徴があります。
日本では中古住宅の評価が低い傾向にありますが、長期優良住宅の認定を受けた物件は、性能・メンテナンス履歴が明確なため、売却時にも高く評価されやすくなります。
また、構造躯体の劣化を防ぐための設計や、維持管理のしやすさが考慮されているため、修繕コストを抑えられる点も見逃せません。
たとえば、一般住宅では20〜30年で大規模リフォームが必要になるケースもありますが、長期優良住宅では定期点検と小規模補修の積み重ねで長寿命化が可能です。
結果として、長い目で見ればメンテナンス費用の総額を数百万円単位で節約できる場合もあります。
つまり、長期優良住宅は「建てた瞬間のコスト」ではなく、「住み続けるコスト」に着目して設計されている住宅です。家計への負担を抑えながら、快適な暮らしを維持できることが大きな魅力です。
〇取得に伴うデメリットと注意点
長期優良住宅は多くのメリットがある一方で、取得や維持にあたって注意すべき点やデメリットも存在します。これらを正しく理解しておくことで、後悔のない家づくりにつながります。
ここでは、主なデメリットと注意すべきポイントを具体的に解説します。
1.コスト増・手続き負担の実態
長期優良住宅の認定を受けるためには、国が定めた複数の性能基準を満たす必要があるため、一般的な住宅に比べて初期費用が高くなる傾向があります。
たとえば、耐震性能の向上や劣化対策、省エネ性能を高めるための断熱材や構造材のグレードアップ、または認定申請のための設計・審査費用などが追加されます。
具体的には、
設計・申請費用:40万〜60万円程度
建築コスト増加分:50万〜150万円程度
が一般的な目安です。
ただし、この費用は建物規模や仕様によって大きく変わります。初期費用だけを見ると高く感じるかもしれませんが、長期的には税制優遇やメンテナンスコスト削減で総合的なコストバランスが取れるケースが多いです。
また、申請手続きもやや煩雑です。
設計図書の作成、性能評価機関への書類提出、行政による審査など、建築会社や設計士と密に連携する必要があります。経験豊富な工務店やハウスメーカーを選ぶことで、この負担を大幅に軽減できます。
2.選ぶ住宅会社・工務店によって変わるリスク
長期優良住宅の品質は、設計・施工を担当する住宅会社の技術力や経験によって大きく左右されます。
すべての工務店やハウスメーカーが長期優良住宅の建築に精通しているわけではなく、申請手続きや性能基準に不慣れな会社を選ぶと、「認定取得に時間がかかる・基準を満たせない」といったトラブルが起こる可能性があります。
また、申請後に建築内容を変更した場合、再申請が必要になることもあります。
そのため、長期優良住宅の建築実績が豊富な業者を選び、最初の設計段階でしっかりと性能要件をすり合わせることが重要です。
さらに、住宅会社が倒産や撤退をした場合、将来の維持保全計画に影響が出ることもあります。
このリスクを軽減するには、建築中や引き渡し後の**保証制度(住宅瑕疵担保責任保険など)を活用し、安心できる体制を整えることが大切です。
3・維持保全を怠ると制度の恩恵が薄れる可能性
長期優良住宅は、建てたあとも継続的な維持管理が求められる点が特徴です。
制度上、「維持保全計画」を策定・提出し、それに基づいて定期点検や補修を実施することが義務づけられています。
もしこの点検・修繕を怠ると、将来的に住宅の劣化が早まり、長期優良住宅としての性能を維持できなくなる恐れがあります。
また、点検記録を残しておくことも重要です。
これらの記録は、将来的に住宅を売却する際の資産価値評価の根拠となります。維持履歴が明確な住宅は、買い手に安心感を与え、リセールバリューの向上につながります。
したがって、長期優良住宅を選ぶ際は「建てて終わり」ではなく、“育てる住まい”として長く付き合う覚悟が必要です。
点検やメンテナンスにかかるコストを計画的に見積もり、定期的なメンテナンスを欠かさないことが、制度の恩恵を最大限に活かす鍵となります。
〇申請・認定までの手続きの流れ

長期優良住宅の認定を受けるには、設計段階からの計画的な準備と行政手続きが必要です。
この流れを正しく理解しておくことで、スムーズに申請が進み、認定遅延や書類不備といったトラブルを防ぐことができます。
ここでは、申請から認定取得までのステップを順を追って詳しく解説します。
設計段階から始まる認定申請のステップ
長期優良住宅の認定手続きは、建築確認申請と並行して進めます。
一般的な流れは以下のとおりです。
1. 設計プラン作成
まず、長期優良住宅の認定基準(耐震性、省エネ性、劣化対策など)を満たす設計を行います。
この段階で、住宅会社や設計士と「認定を目指す」ことを明確に共有しておくことが重要です。
2. 必要書類の作成・性能評価
設計内容に基づいて、評価機関(登録住宅性能評価機関など)が性能評価書を作成します。
これには耐震計算、省エネ性能の評価、維持保全計画書の作成などが含まれます。
3. 所管行政庁への申請
性能評価書を添付して、建築予定地を管轄する自治体(市区町村)へ認定申請を行います。
申請は、建築確認申請の前または同時に行うのが一般的です。
4. 審査・認定通知
自治体が書類を審査し、基準を満たしていれば「認定通知書」が交付されます。
この認定を受けて初めて、長期優良住宅として建築・税制優遇が適用されます。
全体の期間は、おおむね1〜2か月程度が目安です。
ただし、設計変更や書類不備がある場合はさらに時間がかかることもあります。
設計段階から認定を見据えた準備を行うことで効率的に進めていく事が大事です。
〇どんな人・家庭に向いているのか
長期優良住宅は、すべての人にとって最適というわけではありません。
しかし、ライフプランや家族構成、資産形成の考え方によっては、非常に高い価値を発揮します。
ここでは、どんな人・家庭に向いているかを、ライフステージ別・目的別に解説します。
ライフステージ別に見る適性(子育て世帯・二世帯・定年後など)
まず、長期優良住宅が特におすすめなのは、長くその家に住み続ける予定がある家庭です。
具体的には次のようなケースが当てはまります。
* 👨👩👧 子育て世帯
子どもが独立するまでの20〜30年間、安定した住環境を維持したい家庭に最適です。
高い耐震性と省エネ性能により、安全性と快適性の両立が可能になります。
* 🏡 二世帯住宅を検討している家庭
長期優良住宅の「劣化対策」や「維持管理性」は、親世帯・子世帯が代々受け継ぐ住まいに向いています。
さらに、将来的にリフォームや間取り変更がしやすい設計にすることで、世代を超えて住み継げる家になります。
* 👴 定年後のリタイア世帯
老後のメンテナンス負担を減らし、安心して暮らせる家を求める方にも適しています。
住宅の耐久性が高いため、「終の住処」として安心感があるのも大きなメリットです。
このように、長期優良住宅は「今の暮らし」だけでなく「将来の暮らし方」を見据えた家づくりを考える人に最適です。
〇まとめ:長期優良住宅は“未来への資産”になる家
長期優良住宅は、「良い家を長く大切に使う」という新しい住宅価値観を形にした制度です。
耐震性・省エネ性・劣化対策など、国が定める高い基準を満たすことで、家族が安心して長く暮らせるだけでなく、将来的な修繕費の削減や資産価値の維持にもつながります。
確かに、設計・申請の手間や初期コストは一般住宅よりもかかります。
しかし、税制優遇・光熱費の削減・メンテナンス性の高さといった長期的なメリットを考えると、結果的に「家計にも地球にも優しい家」と言えるでしょう。
子育て世帯から二世帯住宅、定年後の住まいまで、“安心・快適に長く暮らしたい”すべての家庭におすすめできる選択肢です。
これからマイホームを検討する方は、将来を見据えた「長期優良住宅」という選択をぜひ一度考えてみてはいかがでしょうか。